進学のプロによる
日本福祉教育専門学校を
ヒモトク

自分らしい未来をひらく、
学生の学びを育むパートナー。
高齢化が進む日本。医療・福祉分野では人材ニーズが急速に高まっているものの、慢性的な人材不足を抱えている。このような社会課題を「学び」で解決しようと取り組んでいるのが日本福祉教育専門学校だ。そもそも医療・福祉分野の職業人になるには国家資格を取得する必要があるが、日福の国家試験合格率は全国平均を大幅に上回っている。なぜか?その鍵となるのが教育に対する日福独自の考え方だ。一般的に専門学校というと学生は教員から「知識や技術を教えてもらう場」とイメージするはず。すなわち教える教員のほうが立場が上となる。しかし、日福は違う。学校の存在を「学生一人ひとりの学びを支援する場」であるととらえ、教職員はあくまでも「学生の目標を実現するパートナー」として対等の立場で学生に寄り添う。だからこそ、学生と教員との間にお互いの信頼関係が醸成され、それが高い国家試験合格率につながっているのだ。また、この寄り添う姿勢はキャリア形成にも生かされている。ライフスタイルが多様化する現代社会において「福祉職もまた多様化すべき」と考え、学生一人ひとりの個性を尊重しながら「自分らしい未来をひらく」キャリア支援に力を注いでいる。資格取得の先を見据えた日福ならではの学びとはどんなものか。早速、ヒモといてみよう。
日本福祉教育専門学校を
知るための3つの視点
01
学び
をヒモトク
多様な学生が集まるからこそ、
一人ひとりにぴったりの学びを。
-テーラーメイド教育-

日福の最大の特長が“テーラーメイド教育”だ。そもそも“テーラーメイド”とは「ぴったりの」「注文したて」という言葉。つまり、テーラーメイド教育とは「一人ひとりにぴったりの学びを提供する」という意味があるという。その内容について岸本校長が語ってくれた。「学びをレベルアップするには3つの要素が必要です。①その人に合った学習方法を見つけること。②モチベーションを高めて維持すること。③学びを習慣化して継続すること。本校ではこの3つを提供するために、教員は常に学生に関心を寄せています。授業を欠席するのは明らかなサインですが、例えば『今日は暗い顔をしている』『勉強に集中できていない』などちょっとした変化も見逃しません。そして、教員から声をかけて悩みごとを解決できる方法を一緒に探ります。とはいえ、教職員と学生との間に信頼関係がなければ悩みは打ち明けてくれませんよね。だからこそ、教職員は一人ひとりに寄り添うことを大切にしています。『常に関心を持ち、寄り添い、信頼関係を築く』。実のところ、これは福祉の専門職業人として働くために重要なのです」(岸本校長)。知識や技術だけではなく、職業人としての姿勢も学んでほしい。これだけでも日福の学生に対する熱意が存分に伝わってくる。
誰ひとり取り残さず、
クラスみんなで合格するために。
-国家試験対策-

医療・福祉系の国家資格は求められる知識の幅が広く、特に社会福祉士では全国平均の合格率が58.1%(2024年3月)と難関資格のひとつといえる。そんな中、2024年度の日福の合格率は昼間部で100.0%、夜間部トワイライトコースで97.4%の実績を誇り、それ以外の国家資格についても全国平均を大幅に上回っている。なぜ日福の合格率は高いのだろうか?社会福祉士養成学科長の秋山先生はこのように語る。「本学科が大切にしているのは限られた時間をどのように過ごすかです。入学直後から学びの生活習慣をつくり、自分はなぜ資格を取得したいのか、自己分析や自己実現シートを作成しながら一人ひとりの想いをはっきりさせることでモチベーションを持続させます。もちろんレベルアップのための個別指導などサポートも徹底的にしますが、大事なのは自主的に勉強できる環境。それを支えるためにもクラスの雰囲気は重要です。そもそも福祉の仕事はチームで助け合い、支え合う仕事。勉強も同じで『自分さえ良ければ』ではなく『みんなで合格しよう』という目標を共有し、教え合い学び合う環境をつくることが重要なのです」(秋山先生)。だからこそ、自分のためにも人のためにも頑張れる人になる。知れば知るほど、日福の学びは想像以上に奥深い。
教科書には書いていない、
現場のリアルを知る。
-オープン講座-

平日の16:30〜18:00に、正規の授業とは別に学科の垣根を越えて自由に参加できる無料のオープン講座を毎週開講している。講座は「福祉業界を知る」「福祉の現状を学ぶ」という2つの項目に分かれており、それぞれの業界に精通した専任教員やゲストスピーカーからリアルな現場を知ることができる。講座を企画・運営する板野氏からその目的や内容について教えてもらった。「オープン講座は毎年4〜11月に開講しています。4〜6月はちょうど就活時期に重なるため、業界全体の理解を深めてもらえるよう福祉業界を知る講座が中心となり、医療、福祉、介護、精神保健などさまざまな分野の内情を知ることができます。それ以降は福祉の現状を学ぶ講座が中心で、2023年度は大手食品メーカーで介護食品を開発している方や、貧困者に対する支援を行うボランティア団体の方をゲストスピーカーとして招きます。『現場のリアルな声が聞けてキャリアの参考になった』と学生からの評判も高く、毎講義とも120名収容の大講義室が一杯になるほどです 」(板野氏)。学生のためになるなら、どんな苦労もいとわない。板野氏を始めとする職員たちの姿勢も、福祉業界に進む人にとってきっと参考になるはずだ。
02
生活
をヒモトク
学びの安心感を生み出す、
クラスメイトとのきずな。
-学びを支える制度-

働きながら通う人、子育て中の人、会社を退職して学んでいる人など、日福では昼間部・夜間部ともに多様な学生が集まっている。時には、仕事やライフイベント、体調不良などによって授業を欠席しなければならないこともあるだろう。そんな時にこそ、クラスメイトがお互いに支え合うのが日福だ。その一つが「ノートテイキング」。これはクラス全員が当番制となってノートやレジュメをファイルし管理していくというもの。もし授業を欠席しても当日の授業内容をキャッチアップできるので知識の不足分を補える。そんな学習環境について、社会福祉士を目指す藤平さんは次のように語る。「学びを支える制度も充実していますし、何よりも年齢や性別を問わず多様なバックグラウンドを持つ学生が集まるからこそ、日々たくさんの刺激を受けています。それぞれの志に触れることで、自分自身の学習意欲も高まります」(藤平さん)。通信課程でも対面授業(スクーリング)の機会があり、ケーススタディやグループワークを行うソーシャルワーク演習を通じて、同じ目標に向かう仲間と考えを共有し合いながら関係性を深めることができる。また福祉現場での豊富な経験を持つ教員が質疑応答も含め丁寧にサポートしてくれるので、「一人ではない」という安心感が学習意欲を高めていく。「きずな」を大切にする日福らしい学習環境といえるだろう。
交通アクセスのよい環境が、
学習とプライベートを
両立させる。
-高田馬場駅から徒歩3分-
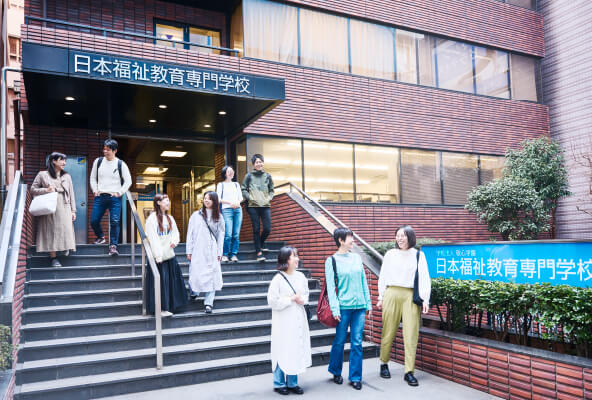
都内屈指の学生街である高田馬場。JR山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線という3路線が乗り入れており、神奈川県・埼玉県・千葉県からのアクセスも良い。社会福祉士学科・昼間部に通う藤平さんは、その魅力を次のように語ってくれた。「仕事でのスキルアップを図るため、自分ならではの強みを身につけたいと国家資格に挑戦。大学時代から馴染みのある高田馬場の立地に惹かれて日福を選びました。自宅のある埼玉県から1時間ほどの通学時間は授業の予習・復習に充てることが多く、効率よく学び進めることができています」(藤平さん)。また、昨年は日福で社会福祉士を取得し、2つめの国家資格を目指して精神保健福祉士養成科・夜間部に通う原田さんにも話をうかがった。「人生100年時代と言われる世の中で、40代を迎えた自分が挑戦したいことは何か。自分と真剣に向き合って出た答えが、誰かのためになる仕事がしたいという想いでした。昼間はボランティア活動に参加することが多いので夜間部に通っていますが、都内のどこからでもアクセスしやすい高田馬場という立地は好都合です」(原田さん)。社会人として働いている方やアルバイトと並行して通う方にとっても、高田馬場駅から徒歩3分の立地は最適といえる。
ライフスタイルに合わせて
無理なく学べる仕組みを。
-多様な学習スタイル-

さまざまなバックボーンを持つ学生が集う日福では、どんな人でも安心して学べる学習環境の仕組みを提供している。例えば、社会福祉士と精神保健福祉士を目指す方には、対面で安心して学べる「通学制」と仕事や育児で忙しい方たちからも好評を得ている「通信制」を用意。通学制では学ぶ時間を選べる3つのコースが設置されており、平日の朝から夕方まで集中して学ぶ「昼間部」、土日休みの週休2日制で16:30から無理なく学べる「夜間部(トワイライトコース)」、18:10からの授業で仕事と両立して資格取得を目指す「夜間部(ナイトコース)」から自分に合ったコースを選ぶことができる。夜間部(トワイライトコース)に通う学生たちに話をうかがった。「私は、『働く・学ぶ・休む』をバランスよく両立するため、平日は週5日アルバイトに励み、勤務時間後は学校の図書館で1時間ほど予習してから授業に臨んでいます。休みの土日にしっかりと休息を取ることも大切です」(西澤さん)。「日中の空き時間は授業の予習と復習はもちろん、『成年後見人』の仕事をする目標をかなえるために、司法書士有資格者の認定試験研修やパソコン教室に通ったりと自己研鑽に励んでいます」(角城さん)。学習を継続するためには、自分らしく無理のない学びスタイルが欠かせない。仕事や家庭と学習との両立に迷っている方は、まず一度日福に相談してみてはどうだろうか。
03
将来
をヒモトク
これからの人生と向き合う、
長く働き続けられる職場探し。
-就職サポート-

日福では学生一人に対して40社以上もの求人が寄せられており、毎年高い就職実績を誇っている。通学部のキャリア支援を担当する五十嵐氏が、希望する将来を実現するために必要なことについて語ってくれた。「専門職として生きるうえで大事なことは、資格を取得して自分は何がしたいのか、ありたい姿を明確にすることです。自己理解と仕事理解がはっきりすると自分の足りないスキルが見つかり、これからどう伸ばしていくか学びのプランが立てられます。さらに、応募先とのギャップも埋まり仕事の定着率も高くなるでしょう。福祉分野は転職の多い業界ですが、就職先をころころ変えているだけで一向にスキルが伸びていかないという事態を防げるのです。」(五十嵐氏)。社会福祉士として働く卒業生の藤岡さんは次のように話してくれた。「実習先を選定する際に、社会福祉学科長の片桐先生から『これまでの経験をどう活かしたいのか、実習で何を知り学びたいのか』を深く考えるよう指導してもらいました。そのおかげで、前職の営業経験で培った対人スキルや経営的視点を活かしながら、知的障がいのある方と就労先をつなぐ就労移行支援施設に行きたいという目標が明確になったのです。実習先ではたくさんの発見が得られましたし、施設長の想いに強く共感して就職にまでつながりました。現在も学びの多い日々が楽しくて仕方ありません」(藤岡さん)。日福は就職することではなく、その先の「ありたい姿」を見据えている。
卒業しても学び支え合い、
福祉の真のエキスパートへ。
-卒後ネットワーク-

就職はキャリアのスタートに過ぎず、現場を経験するたびに悩みや心配ごとも生まれるはず。だからこそ、同じ職を志す仲間が集い情報を共有し合えるネットワークの存在がとても重要になる。そのため日福では各種講座や講習会をそろえた「日福アカデミー」のほか、「ソーシャルワーク実践研究会」や「精神保健福祉研究科」などそれぞれの分野に進んだ卒業生が集える各種ネットワークを構築している。言語聴覚療法学科の馬目先生に、その重要性について話をうかがった。「超高齢化社会において言語聴覚士の需要は高まる一方、人材不足により施設や病院にただ一人の存在ということも少なくありません。専門性を高めていくためには個人で外部の有料セミナーを受講するのが一般的とされる中、日福では『SLHT(Speech, Language, Hearing, Therapy)研究会』を開催することで、各領域の第一線で活躍する卒業生がお互いに学び合う場を提供しています。参加費は無料で年4回開催しており、毎回30名ほどの卒業生が集まります」(馬目先生)。創立から40年にわたり、福祉教育のパイオニアとして数多くの卒業生を社会に輩出している日福。在学中のみならず卒業後も「人と人との関係」を大切にする環境があるからこそ、「きずな」という人生にとってかけがえのない財産を手に入れることができるのだと、あらためて実感した。
「福祉×〇〇」でこれまでにない
オンリーワンのキャリアを。
-福祉の新たな可能性-

「福祉」とは一般的に「幸せ」や「豊かさ」を意味するが、その実現方法は人それぞれであり、時代のニーズに合わせて変化する。在学生の角城さんは、これまでの人生経験と福祉をかけ合わせてオンリーワンの未来をひらこうとしている。「40代を目前に人の役に立つ人生を歩みたいと思い立ち、知的障がいなどによって判断能力が不十分な方の代わりに法律行為を行う『成年後見人』に興味を持ちました。そしてその2本柱である『財産管理』とご本人の生活を支える『身上保護』を行ううえでそれぞれの専門性を身につけたいという思いから、法律に精通すべく約5年間かけて司法書士試験に合格し、現在は日福で精神保健福祉士の資格取得を目指しています。実習先の選定においては、先生から『将来自ら事業所を立ち上げるためには人脈づくりが大切だ』と、地元県の施設と病院を紹介いただきました」(角城さん)。また卒業生である田中さんも独自のキャリアを歩んでいる一人だ。「大学で、家族法に関わる『児童虐待』の問題に関心を持ちました。多くの友人が就職する中、社会的に弱い立場にある子どもたちのために行動を起こしたいと社会福祉士を志し、大学卒業後に日福へ進学。現在は児童養護施設に勤務し、個性豊かな子どもたちの人生と向き合っています。これからも子どもたちはもちろん、福祉の現場で働く職員の幸せにも寄り添えるよう、専門的に学んできた労働法をはじめとする法律の知識を活かしていきたいです」(田中さん)。人の数だけ新たな可能性があるのが福祉の世界。さあ、あなたは福祉と何をかけ合わせるだろうか。